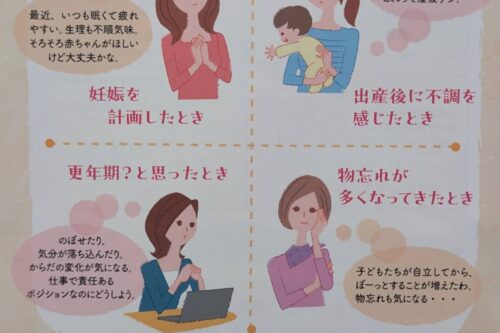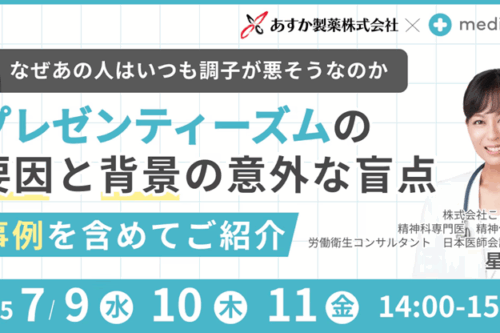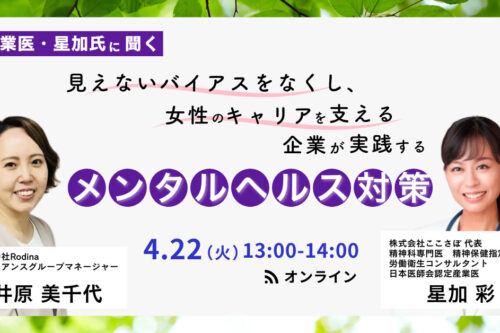職場のうつ病対策 Part1|企業が取り組むべき予防対策と早期発見のポイント

「最近、うつ病で休職する社員が増えてきた」
「メンタル不調で突然辞めてしまった」
このような話を、社内外で耳にすることが多くなっていませんか?
うつ病は、決して特別な人がなる病気ではありません。
日本人の約15人に1人が経験するとも言われており、誰にでも起こりうる身近な心の病です。[1]
だからこそ、企業として「うつ病になりにくい職場づくり」や「早期に気づける体制づくり」が重要になっています。
とはいえ「何から始めればよいのかわからない」「うつ病と気づくにはどうしたらよいの?」と悩むものです。
この記事では、うつ病になりやすい人の特徴や職場でうつ病になりやすい状況、職場でできるうつ病対策について具体的に紹介します。
社員の心の健康を守るために、今できることから始めましょう。
目次
うつ病になりやすい人の特徴と職場でわかる症状
うつ病は、年齢や職業などに関係なく誰でもなりうる心の病気です。
性格や心の弱さにより発症するわけではありません。
ただし、うつ病になりやすい人には以下のような特徴があります。[1]
【うつ病になりやすい人の特徴】
- 完璧主義
- 柔軟性がやや乏しい
- 真面目で責任感が強い
- 人に相談することが苦手
- 自分の考えを伝えるのが苦手
- 社交的で気を使いすぎてしまう
- 優先順位をつけられず、ひとりで抱え込みがち
うつ病になると、一日中気分が落ち込んでいたり何をしても楽しめなかったりする精神症状がみられます。ほかにも、身体的な症状では眠れない・食欲がない・疲れやすいなどの不調がみられ、日常生活に支障がでることもあるでしょう。
うつ病の症状について、次で詳しく解説します。
職場で社員がうつ病か気づくサインと症状
社員がうつ病か気づくサインと症状を以下の3つに分けてみていきましょう。
それぞれ詳しく解説します。
自覚症状
うつ病の症状だと本人が不調に気づいていないケースもありますが、自覚症状として以下のような症状が挙げられます。
【自覚症状】
次のうち5つ以上(1か2を含む)が2週間以上続くときは、うつ病の可能性があります。
- 悲しく憂うつな気分が一日中続く
- これまで好きだったことに興味がわかない、何をしても楽しくない
- 食欲が減る、あるいは増す
- 眠れない、あるいは寝すぎる
- イライラする、怒りっぽくなる
- 疲れやすく、何もやる気になれない
- 自分に価値がないように思える
- 集中力がなくなる、物事が決断できない
- 死にたい、消えてしまいたい、いなければよかったと思う
企業にはこうした症状に早く気づけるように、必要なサポートや医療機関への受診を促せる体制が求められます。
周囲の人がわかるサイン
うつ病は、本人が気づかないうちに進行してしまうこともあります。
以下のような変化がみられるときは、本人がつらさを抱えている可能性があります。
【周囲の人がわかるサイン】
- 表情が暗い、笑顔が減った
- ネガティブな発言が増えた、自分を責めてばかりいる
- 涙もろくなった
- 反応が遅い
- 落ち着かない
- 飲酒量が増える
出典:うつ病|こころの情報サイト 国立精神・神経医療研究センター
本人が症状に気づいていないケースでは、周りが変化に気づけるかどうかが早期対応のポイントとなります。
とくに「いつもと違うな」と感じる言動や表情の変化は、見逃してほしくないサインのひとつです。
職場でわかるサイン
とくに職場では、以下のような症状がみられるときに注意が必要です。
【職場でわかるサイン】
- 毎日疲れている
- 休みや遅刻、早退が増える(とくに当日の朝、急に生じる場合)
- 仕事でのミスが増える
- 仕事に集中できない、同じ仕事量なのに時間がかかるようになった
- 業務時間内に居眠りをしている
- コミュニケーションが減った
職場でわかりやすい症状としては、朝起きられなくなったり、出勤前に調子が悪くなって遅刻したりするなどがあります。
これは、うつ病の特徴のひとつで、朝に症状が強くでて午後から夕方にかけて少しずつやわらぐ傾向があるためです。 [2]
ほかにも、うつ病の症状のひとつとして夜眠れなくなることがあります。
そのため、業務時間内に眠気が生じたり、仕事に集中できないためミスが増えたりするでしょう。
その結果、仕事が終わらずに残業が増えて、更にうつ状態が悪くなるという悪循環を起こしてしまうことがあるのです。
職場でうつ病になりやすい具体的な状況
うつ病になる要因は、必ずしも1つとは限りません。
仕事・プライベートのストレスや環境の変化、個体側要因などさまざまな要因が重なり合い、うつ病を発症すると考えられています。
ここでは、職場でうつ病になりやすい状況を、業務内容と人間関係に分けて解説します。
業務内容
以下のような業務内容は、うつ病になりやすいと言われています。[3]
- 達成が難しいノルマ
- 責任が重すぎる仕事内容
- ひとりで抱えきれない仕事量
- 長時間労働が長期間続いている
- 裁量権(自分で決める権利)がない
- 仕事内容・仕事量の大きな変化があった
- 苦手とする業務内容をずっと強いられている
業務内容によるストレスは、社員の心の負担になります。
とくに「自分の力ではどうにもできない」と感じる状況が続くと、無力感を覚えたり、達成感を得ることができずに心が疲れてしまいます。
また、仕事内容が自分の特性や得意分野と合っていないときも、毎日のストレスとなり本人も気づかないうちに心身の不調につながってしまうことがあるのです。
人間関係
以下のような人間関係は、ひとりでストレスを抱えやすくなるため、うつ病になりやすい状況と言えるでしょう。[3] [4]
- 気軽に相談できる人がいない
- 思うように上司から評価されていない
- 周囲からサポートされていないと感じる
- 休日や勤務時間外にも仕事の連絡がきて対応しなくてはならない
- 上司や顧客や取引先等から、身体的攻撃・精神的攻撃等のハラスメントを受けた
こうした人間関係のストレスは、孤独感や無力感につながりやすく、うつ病のリスクを高めます。
とくに、誰にも相談できずひとりで抱え込んでしまう状況は、心の負担が大きくなりやすいため注意が必要です。
こうした状況を改善するために、企業として社員が安心してSOSを伝えられる環境づくりが求められます。
職場でできるうつ病への対策
職場でできるうつ病対策として、以下の4つが挙げられます。
「社員がうつ病かも」と思ったら、必要に応じて産業医や保健師など専門スタッフと協力し、職場でのうつ病対策をしましょう。
また、うつ病の症状はほかの病気で生じることもよくあります。
「少し様子をみようかな…」と先延ばしにせず、早めに精神科受診を促すことが大切です。
コミュニケーションがとりやすい環境をととのえる
社員が心の不調を抱えていても、「忙しそうで話しかけにくい」「こんなことで相談していいのかな」と相談することをためらい、誰にも言えないまま症状が悪化するケースも少なくありません。
だからこそ、日ごろから相談しやすい雰囲気づくりが大切なのです。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- 休憩室やエレベーターの近くにポスターを掲示する
- 社内メールや掲示板で「こころの相談窓口」を定期的に案内する
- 朝礼や定例会で「気になることがあれば遠慮なく相談を」と繰り返し伝える
たとえば、上司や先輩から「いつでも相談してね」と声をかけたり「最近、調子どう?」と何気ない会話を意識的に増やしたりするだけでも、社員は相談しやすくなります。
職場全体で「ひとりで抱え込まないように」と啓発することで、「相談すること=悪いことではない」という相談しやすい雰囲気づくりにつながります。[5][6]
小さな積み重ねにより、社員が気軽に悩みを打ち明けられる空気が職場に生まれ、うつ病の早期発見や深刻化を防ぐきっかけとなるのです。
社員自身のポジティブ・メンタルヘルスを高める
うつ病を防ぐには、業務上のストレスを減らすだけでなく、社員自身の心を健やかに保つ力を育てることも大切です。
そのために有効とされているのが「ポジティブ・メンタルヘルス」の考え方です。
たとえば以下のような方法は、誰でも取り入れやすく日々の心のケアにつながります。[1] [7][8]
- マインドフルネス:呼吸や今の感覚に意識を向け、気持ちが落ち着ける方法
- ウェルビーイング:仕事だけでなく、健康や人間関係、人生の満足度など、将来も含めた長期的な幸せを感じられる状態。「心地よくいられること」を大切にする考え方
- アサーティブ・コミュニケーション:自分の気持ちや言いたいことを相手に上手く伝える方法
こうした内容をテーマに、社員向けの勉強会や資料の配布を行うことで、自分の心と向き合うきっかけにもなります。
「こんなとき、どうやってストレスとつき合ったらよいの?」と考えるだけでも、気づきが生まれるでしょう。
また、ストレスチェックを活用して、社員自らが自分のストレス状態を客観的に知ることも大切です。
上司や管理職のメンタルヘルスについての知識や意識を高める
うつ病の早期発見には、社員本人が「気づいて伝える力」だけでなく、まわりが気づいて声をかける力も欠かせません。
日ごろから接している上司や管理職が社員の心の不調に気づくためには、メンタルヘルスに関する基本的な知識や意識を持つことが大切です。[5][6]
たとえば、以下のような取り組みが効果的です。
- 管理職向けのメンタルヘルス研修の実施
- 心の不調に関する資料やチェックリストの配布
- 「どんな変化があれば相談するべきか」を学ぶ場の提供
こうした取り組みを行うことで、上司が「最近ちょっと元気がないな」「話しかけても反応が違うな…」といった小さな変化に気づけるようになるでしょう。
社員の心に寄り添える職場づくりは、まずは「気づく力」と「支える仕組み」が欠かせません。
上司や管理職がひとりで抱え込まないためにも、企業としてメンタルヘルス対策に取り組むことが大切です。結果的に、職場全体の信頼関係の構築や社員全体の安心感につながっていきます。
職場環境をととのえる
社員は1日の多くの時間を職場で過ごしています。
だからこそ、社内の明るさや空調、レイアウトなどもストレス原因になるため、職場環境をととのえることが大切です。
令和3年12月に職場における労働衛生基準の一部が見直されました。[9]
具体的には以下のように環境をととのえましょう。
- 照明の調整:
オフィス全体は明るくても、実際に作業する机が暗いこともあります。一般的な事務作業では300 ルクス以上が基準です。社員一人ひとりの環境にあった明るさを確保することが大切になります。
- 休養室や休養所の設置:
いつでも利用できる、静かに過ごせる休養室や休養所のような「ゆっくり休める場所」があるだけでも、社員の安心感は大きく変わります。
- 温度管理:
令和4年4月1日より、社員が常に働いている部屋の温度基準が変更になりました。
17度以上28度以下→18度以上28度以下
過度な冷暖房は身体的な不調につながることがあります。快適な室温で過ごせるように心がけましょう。
ほかにも、観葉植物を置くだけでも空間の印象がやわらぎ「気軽に話しかけてもいい雰囲気」が生まれることもあります。
まずは取り組みやすいことから、職場に心地よさを増やしていきましょう。
まとめ
うつ病は、誰にでも起こりうる身近な心の不調です。
職場でのストレスや人間関係の悩みが原因になることも多く、企業としての予防対策が求められています。
社員が安心して働ける環境づくりには「気づく力」と「相談しやすい雰囲気」、そして「支える仕組み」が大切です。
小さな取り組みの積み重ねが、職場全体の心の健康を支える力となるでしょう。
まずは「ここならできそうかな?」と思うものから一歩ずつ取り組んでください。
【参考文献】
[1] うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)p3 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
[2] 職場における自殺の予防と対応 Q&A|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/03_0054.pdf
[3] WHO職場のメンタルヘルス対策ガイドラインの紹介p3|今村幸太郎、堤 明純、川上 憲人https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258075.pdf
[4] 仕事上のストレスで精神障害に 労災認定 昨年度は最多1055人|NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250625/k10014844151000.html
[5] 日本の正社員労働者における職場のソーシャルサポートと精神的健康の関連―縦断調査による検討―p15結論|加島 遼平、高田 琢弘、小林 秀行、王 薈琳、佐々木 毅、高橋 正也https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjhep/36/2/36_2024.14/_article/-char/ja
[6] 職場のメンタルヘルス対策ガイドラインp43|世界保健機関(WHO)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
[7] 瞑想Meditation|eJIM 厚生労働省
https://www.ejim.mhlw.go.jp/pro/overseas/c02/07.html
[8] ウェルビーイングの向上について|文部科学省
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000214299.pdf
[9] ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf