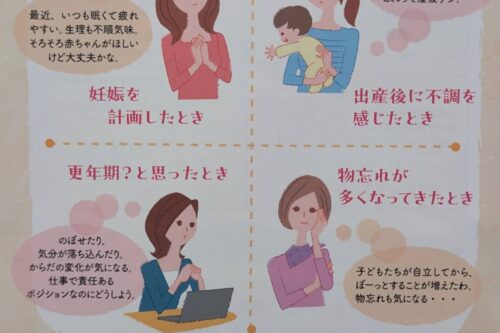企業が従業員の健康を守るために知っておくべき熱中症対策

2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されました。
職場の熱中症対策は万全ですか?
出典:業務上疾病調査|厚生労働省((死傷者は休業4日以上、死傷者数には死亡者数を含む)
熱中症は、死亡災害となる割合が他の災害と比べて5〜6倍とリスクが高くなっており、死亡者数は年間30人を超える年もあります。その約7割が屋外作業中に発生しています。昨今の気温上昇の傾向から、さらに災害の増加が懸念されているのです。
そのため、企業は従業員の健康を守るために「職場での熱中症対策」が重要です。熱中症の死亡災害のほとんどが、初期症状の放置や対応の遅れによるものといわれています。
この記事では、熱中症の基礎知識から、職場や個人でできる予防策、そして現場での具体的な対応方法までを解説していきます。この記事を読んで、従業員の熱中症の重症化を防ぐ対策を検討してみましょう。
目次
熱中症の基礎知識と症状の段階
熱中症とは、気温や湿度が高い環境で体温調節機能が正常に働かなくなり、体内に熱がこもることで発症します。放置すれば重症化し、命に関わるリスクもあるため、早期の発見と対応が重要です。
熱中症の症状は進行度に応じて重症度I〜IIIの3段階に分類され、以下のようにそれぞれ対応方法が異なります。
| グレード | 症状 | 対応 |
| 重症度Ⅰ(軽症) | ・意識はある ・手足のしびれ、こむら返り ・めまい、立ちくらみ ・汗が引かない | ①涼しい場所に移動し、衣服を緩める ②身体を冷やしながら、水分・塩分を補給する ③症状が改善しない場合は医療機関を受診 ※この段階でも必ず誰かが付き添い、様子を見守ることが重要です |
| 重症度II(中等症) | ・意識はあるが、様子がおかしい ・判断力、集中力の低下 ・頭痛、吐き気、強い倦怠感 | 速やかに医療機関を受診する |
| 重症度III(重症) | ・意識がない、または反応が鈍い ・呼びかけに対して返答が不明瞭 ・けいれん、ふらつき、体温が高く全身が熱い | ①ただちに119番に通報し、救急車を要請 ②到着までに積極的に身体を冷却しながら対応を継続 |
現場での初期対応の遅れは、症状の急激な悪化を招く恐れがあります。「少し様子が変だな?」と感じたら、熱中症かもしれません。すぐに作業を中断し、周囲の人や現場の責任者に連絡してください。最初の判断と行動が従業員の命を守る鍵となります。
従業員一人ひとりができる熱中症予防策
熱中症は、企業の管理体制とあわせて個人の心がけも大きな予防効果につながります。ここでは、屋内外で働く従業員が日常的に取り入れやすい予防策を紹介します。
| 屋外 | ・帽子や日傘など、直射日光を遮るアイテムを着用する ・通気性の高い綿、麻素材の衣類を選ぶ ・特に暑さが厳しい正午〜午後3時の外出はできるだけ避ける ・「汗がかける身体づくり」のため、日頃から軽い運動を習慣にする |
| 屋内 | ・室温は28℃以下を目安に設定 ・無理な節電はNG。サーキュレーターやすだれなどをうまく活用する ・湿度にも注意し、こまめに換気を行う ・疲労により体温調節が乱れるため、十分な休息を取り体調管理を心がける |
| 飲み物 | ・水分は食事からの摂取も含め、1日2リットル以上が目安 ・冷たい飲み物の飲みすぎには注意・状況に応じて飲み物を選ぶ 脱水時:スポーツドリンク(糖分のとりすぎに注意)、経口補水液 普段の水分補給:水、麦茶など ※カフェインやアルコールの含まれる飲料は避けましょう |
| 食べ物 | ・汗により失われやすいミネラルの補給 マグネシウム:昆布、納豆 カリウム:ほうれん草、豆類 ・ミネラルの吸収を助ける食品 クエン酸:レモン、梅干し ・エネルギー産生をサポート ビタミンB1:ウナギ、豚肉 |
また、飲酒により熱中症のリスクは高まります。仕事の前日は飲酒を控えめにして、ぐっすり眠るのがおすすめです。
熱中症の危険性があるかどうかは、環境省の「熱中症警戒アラート」を参考にするといいでしょう。前日夕方17時と当日の朝5時頃に発表されるため、事前に確認しておくといいでしょう。
熱中症のリスクが高い人
熱中症はすべての人にとって危険ですが、特に発症リスクが高い人たちが存在します。以下に当てはまる方は、事前の対策と周囲の配慮が特に重要です。
- 高齢者やこども
- 持病があり、薬を内服している人
- 手足や体幹に障害がある人(特に車椅子利用者)
高齢者やこどもの場合は、体温調節機能がうまく働かないため大人よりも暑さの影響を受けやすくなっています。
持病がある人の中でも特に心臓疾患や糖尿病の持病がある人は重症化しやすいでしょう。また、発汗抑制や抗利尿作用の薬を飲んでいる人も注意が必要です。
身体に障害のある人は、暑さを感じにくかったり、汗をかけなかったりするためリスクが高くなります。また、車椅子を利用している方は、地面からの照り返しが強くなるため、より注意が必要です。
他にも肥満や、運動をしない・体力がない、暑さに慣れていない、二日酔いや下痢嘔吐などの症状がある体調不良の人も熱中症リスクが高くなります。
このように、さまざまな理由で熱中症のリスクが高くなる人がいるため、事前の対策が重要です。こまめな休憩や水分・塩分補給を習慣にすることはもちろん、周囲の人が体調の変化に気づきやすい環境を整えることも大切です。
とくに管理者や同僚は、日頃から声をかけ合い、異変を感じたときにはすぐに対応できるよう備えておくことが、現場全体の安全につながります。
職場の熱中症対策が義務化されます
2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務となりました。違反した場合は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金という罰則が設けられています。
企業は従業員の安全を守るために、「見つける」「判断する」「対処する」の3つの対応を行うことが義務付けられています。
- 熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で速やかに報告・共有する体制整備
- 重症化を防ぐ応急処置・医療機関への搬送手順の作成
- 関係者全体へ周知する仕組みの構築(例:朝礼、掲示、イントラネット等)
【熱中症の恐れがあるものに対する処置例】
義務対応が必要となる作業環境は以下のような場所です。
- WBGT値(暑さ指数)28℃以上の環境 または
- 気温31℃以上の環境1時間以上の環境で、連続1時間以上作業または1日4時間を超えての実施が見込まれる作業
この条件に該当する作業現場は、義務対応の対象です。それぞれの作業現場の実情に合った社内体制の整備、応急処置の手順(フロー図)の作成をして関係者に周知しましょう。事前に確実に熱中症に備えることが大切です。。
熱中症リスクを数値で管理するための指標「WBGT(暑さ指数)」とは
企業が現場で熱中症対策を徹底するには、「感覚」ではなく「数値」での管理が不可欠です。その基準となるのが「WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)」です。
このWBGTは、気温・湿度・日射・気流といった4つの要素を取り入れているため、より実態に近い暑さの指標となっています。
仕事の前に、WBGT指数計で職場の暑さ指数を測定します。暑さ指数が測定できない場合は熱中症予防情報サイトで確認も可能です。日差しがない室内では気温と湿度からWBGTを簡易的に算出できます。
計測するときは「身体作業強度等に応じたWBGT基準値」を参照し、基準を超える場合は作業場所のWBGT値の低下や身体作業強度の低い作業へ変更しましょう。それでも基準値を超えてしまう時には更なる熱中症対策をおこなう必要があります。
WBGTを計測する場合は、市販のWBGT測定器(JIS規格を満たした黒球付きのものを選びびましょう)を使うことで、現場の暑さリスクを即座に数値化することができます。朝だけでなく、正午前後や作業中など、定時測定のルールを決めて習慣化することで、現場全体の意識向上にもつながるでしょう。また、建設現場のように環境差が大きい場所では、日向・日陰・足場上など、作業エリアごとに測定することも重要です。
管理者が行うべき作業者のチェックポイント
熱中症を予防するために、管理者は仕事前や仕事中に従業員の体調を把握しておく必要があります。
【仕事前】
よく眠れたか:夏は寝苦しくて睡眠時間が短くなりやすいです。
食事をしたか:食事で水分・塩分・糖質などしっかり栄養を摂取しましょう。朝食も大切です。
体調は良いか:風邪気味、下痢嘔吐の有無など確認します。持病のある方は服薬確認も重要です。
二日酔いしてないか:二日酔いの時点ですでに脱水状態です。
熱中症警戒アラートの確認:当日の朝アラートが発表された場合は作業の見直しも要検討する。
【仕事中】
単独作業を避け、声をかけ合う:⼀⼈作業の場合、周囲の⼈が積極的に声をかける。
監督者は現場パトロール:作業員に声をかけ、安全確保に努める。
⽔分・塩分の補給:のどが渇いていなくても、こまめに⽔分と塩分を摂る。
こまめに休憩:休憩中にできるだけ⾝体を冷やしましょう。
休憩時間・水分&塩分補給について
暑い現場では、自分が思っている以上に体から水分が失われています。実は、のどの渇きを感じたときには、すでに脱水状態です。
そのため、作業中は「のどが渇いたから飲む」のではなく、時間を決めて定期的に水分と塩分を補給することが大切です。目安としては、30分ごとにコップ1杯(約200ml)の水分と塩分を摂るのがおすすめです。
また、発汗が多い現場では、ただの水だけでなくスポーツ飲料や経口補水液を併用することで、ナトリウムなどの電解質を効率よく補給できます。糖分が気になる方は、「カロリーオフ」や「糖質ゼロ」の製品を選んだり、家庭で経口補水液を手作りする方法も有効です。
⼤量に汗をかいて⽔分と塩分が減った状態のときに⽔だけを補給すると、体内の塩分割合が低下して熱中症になるリスクがあります。⽔だけを飲むのではなく、必ず塩分も⼀緒に補給してください(塩あめだけ舐めるのも効果はありません)
脱水は放置すれば、めまい・けいれん・意識障害といった熱中症のリスクへ直結します。「自分は大丈夫」と思わず、職場全体で補給タイムを設けるなど、仕組みとして取り入れることが安全対策につながります。
暑熱順化で“暑さに強いカラダ”をつくる:熱中症予防のカギ
熱中症対策というと「水分補給」や「冷却」に目がいきがちですが、実は「暑さに慣れること=暑熱順化(しょねつじゅんか)」も重要なポイントです。
暑熱順化とは、暑い環境に少しずつ身体を慣らしていくことで、早い段階で汗をかいて体温上昇を抑える仕組みを整えることです。このプロセスを経ることで、熱中症のリスクを大幅に減らすことができます。
実践方法と期間の目安
暑熱順化は、無理のない範囲で日常的に汗をかく習慣をつけることで実現できます。
- 少し早歩きで通勤する
- 入浴時に湯船につかる
- 軽い運動を日中に行う
このような習慣を数日〜2週間ほど継続することで、体が暑さに対応できるようになります。
特に注意が必要なタイミング
暑熱順化は一度習得しても、数日間暑い環境から離れると効果が薄れることがあります。特に以下のタイミングでは、意識的に暑熱順化を促すことが大切です。
- 作業初日
- 長期休暇明け(盆休み・年末年始など)
- 急激に気温が上がった日
企業は、作業前の教育や朝礼などで暑熱順化の重要性を繰り返し伝えることが、現場での事故防止につながります。
現場でできる!脱水・熱中症リスクを見逃さない8つの工夫
熱中症は「気づいたときには手遅れだった」というケースも少なくありません。だからこそ、日常のちょっとした工夫やチェック習慣が、従業員の命を守るための第一歩になります。
ここでは、企業や建設現場、工場などで実践されている「脱水・体調チェック」「休憩・冷却」「見える化」などの8つの工夫をご紹介します。
- 皮膚をつまんで脱水チェック
手の甲の皮膚をつまんで離し、元に戻るまで2秒以上かかる場合は脱水の疑いがあります。特に高齢者ではこの方法が有効です。 - 爪押しで隠れ脱水を確認
爪の色が白から元の色に戻るスピードが遅い場合、血流や水分不足のサインかもしれません。厚労省も推奨するシンプルな確認方法です。 - 尿の色で脱水を判別
濃い黄色や茶色に近い尿は脱水状態を示している可能性があります。トイレのたびに気軽にチェックできるセルフモニタリング手段です。 - 平均台を使った体調チェック
平均台や直線を歩いてふらつきやバランスの乱れがないかを確認します。単純な動作でも、身体の不調にいち早く気づけます。 - 車を「休憩所」にアレンジ
空調が効いた車内を休憩スペースに活用し、体をしっかり冷やすことができます。工事現場などでは特に有効な方法です。 - 足水で身体をクールダウン
足を水に浸すだけでも体の深部体温を効果的に下げられます。バケツを用意するだけで簡単に取り入れられる工夫です。 - ウェアラブル端末で体調の見える化
熱中症リスクの予兆検知やSOS発信、位置測定など、さまざまな機能を備えた端末が増えています。自社に合ったものを導入することで、安全管理が強化されます。 - ドリンクサーバーで水分補給を習慣化
目につく場所に設置することで、従業員に水分補給を促せます。とくに衛生服やマスク着用で蒸し暑くなりやすい職場では、効果的な取り組みです。
熱中症対策は、特別な設備や大きな仕組みだけではありません。日常のちょっとしたチェックや環境づくりが、命を守る第一歩になります。体調のサインに気づき、こまめな休憩と水分補給を促し、現場全体で「声をかけ合う空気」を育てることが重要です。
まとめ:職場全体で命を守る熱中症対策を
「熱中症」は、発見が遅れれば命に関わる重大災害につながります。熱中症のリスクを最小限に抑えるためには、早期発見と迅速な初期対応、そして日頃からの体調管理が不可欠です。
十分な食事と睡眠で体調を整え、外出時や作業中には熱中症対策を万全にしましょう。高齢者や持病を持つ方など、重症化リスクのある方は特に注意が必要です。
また、有効な対策は職場ごとに異なります。作業環境や業務内容を見直し、現場に即した熱中症対策を計画・実施しましょう。法令の遵守はもちろん、緊急時の連絡体制や行動フローをあらかじめ定め、全従業員に周知徹底することが重要です。
職場での熱中症を防ぎ、大切な社員の命を守ることが、企業としての責任であり、信頼にもつながるでしょう。